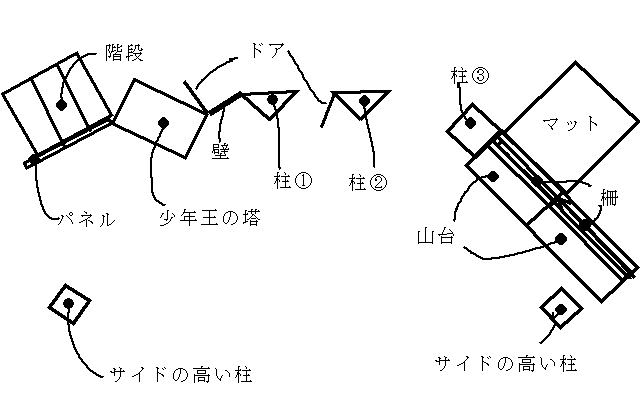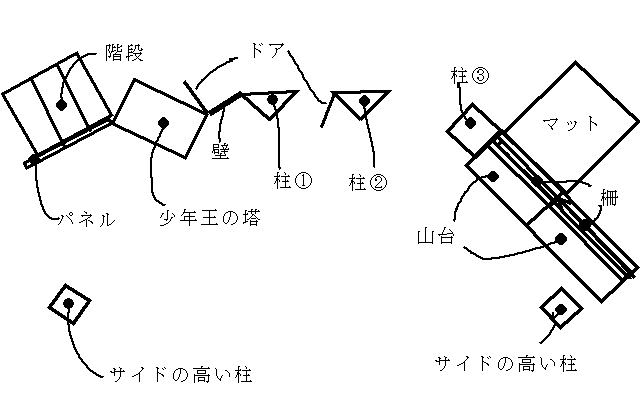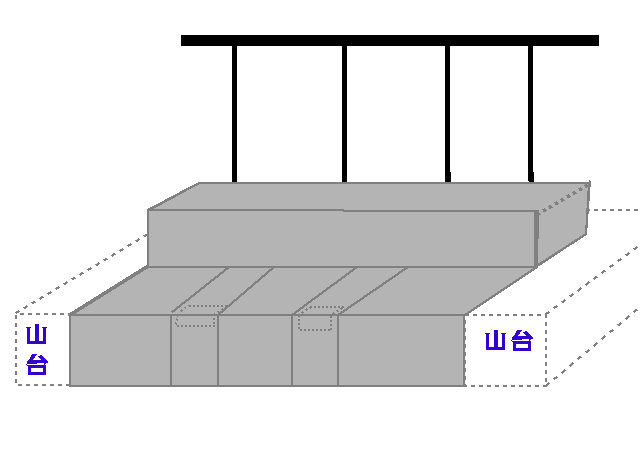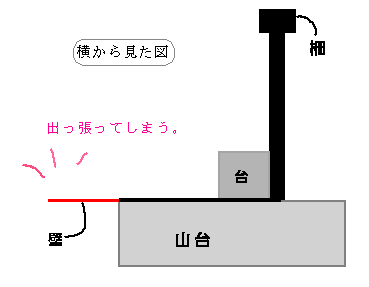大道具徹底解体!!
大道具の配置は基本的に動きません。
場面に応じてドアが出たり,壁が出たりしました。(裏方が劇の間中柱の影にこっそり隠れて動かしました)
そして,最も注目すべきは柵の部分。
この劇の舞台づくりで最も工夫された点は「校庭から屋上への場面の移り変わりのあらわしかた」というところでしょう。
劇の内容上,「柵」はどうしても必要となります。
しかし,「柵」があるとどうしても校庭に見えにくい・・・
そんなわけで考案されたのがこの↓「柵」。
この「柵」の部分は角材でできていて,「壁」の部分はベニヤ板でできています。
この二面は「台」(コンパネで出来ている)を中心にして簡単に90°回転させることができます。
「壁」を起こすとこう↓なります。
なぜ「壁」の部分を切っているのかというと、斯文祭後、柵の存在感がない、ということで山台をつけて高さをアピールしたのですが、その時に問題が一つ。
それまでの普通の状態のベニヤの壁だと「柵」にしたときに図↓のようにベニヤ板が突き出てしまうのです。
山台をあまり大きくしすぎても壁にしたときにおかしいことになります。第一舞台が狭くなる・・・
というわけで「壁」の部分のベニヤをふたつに切って,蝶番でつける、という策をとったのです。
こうすると,邪魔にならず,今までの壁の高さもキープできるというわけです。
また,おこしたときに壁が倒れてしまわないように使った物はクリップとフックとひも。
フックをつけたひもを柵にこっそりくくりつけて、壁を起こしたときには壁につけたクリップにフックを引っかけて壁が倒れないようにしました。
・・・とまぁ、こんなからくりがあった舞台だったのです。
原案を出していただいた櫻井さん。
何時間も木材コーナーで居座る高校生らにも快くアドバイスをして下さったJ●Yの方々。
練習場所にいきなり出没しても嫌な顔ひとつせず、それどころか応援までして下さった(たとえ私らあてでなくとも)丸高応援部の皆さん。(石庭汚しまくってごめんなさい。)
などなど、多くの方へ、本当にご迷惑をおかけしました。
そして、本当〜に、有り難うございました。